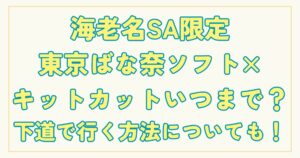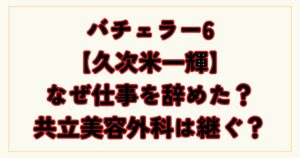映画『ゆきてかへらぬ』は、詩人・中原中也の同じ名前の詩をもとに作られたました。
静かで切なく魅惑的な雰囲気をもつ作品です!
この作品では、「後戻りすることのない3人の人生」が描かれています。
文学作品をテーマにしているからこそ、ささいな台詞・演技はもちろん、それぞれの場所や小道具からも表現され、感性が刺激されます。
そこで、2度登場する乳母車は、物語の核となるテーマを静かに伝える重要なアイテム!
この記事では、「映画に登場する乳母車は何を表しているのか?」という視点から、この作品を読み解いていきます。
中原中也の詩と映画のつながりにも触れながら、分かりやすく解説していきます!




乳母車が登場する場面
乳母車が登場する場面①
最初の登場は川岸。
中原中也が「僕がいるんだ、あの中に」と指す乳母車には、赤い風車が付けられており、風に吹かれて回っています。
彼の言葉に続いて、長谷川泰子が「分かるわ。私の母も神経が壊れやすくてね」と語ります。
このシーンではセリフはほとんどなく、風車が静かにくるくると回る音と映像のみが数秒間続きます。
意味深な沈黙が観る者の感性を刺激します。
乳母車が登場する場面②
お墓での撮影現場に表れた中原中也と小林秀雄!
中原中也がやつれた様子で、空っぽになってしまった乳母車を押しています。
ここに乗っているはずの「何か」がいない、つまり「喪失」や「不在」が、強烈な静けさとともに描かれています。
ゆきてかへらぬの詩に出てくる乳母車
【原文の一部】
風車を付けた乳母車、いつも街上に停つてゐた。
【現代語訳】
風車をつけた乳母車が、いつも町の中に止まっていた。
この一行は、映画のビジュアルにも直接的に反映されており、詩と映像とが連動しています。
乳母車が象徴するものとは?
1. 命の始まりと終わり
乳母車は、本来「命のはじまり」や「赤ちゃん」の象徴です。
しかし映画に登場するそれには赤ちゃんがいません。
その空っぽさこそが、「誰もいない」「何かが終わった」ことを静かに、しかし強く印象づけています。
「かつてはいた」「孤独」「もういない」という余韻を与え、命の儚さと同情の感覚を同時に思い起こされました。
2.風車=見えない力、不安定な世界
乳母車につけられた風車は、風という「目に見えない力」で動きます。
風車が風にくるくる回る様子は、時間、運命、感情など、自分の意思ではどうにもならないものを象徴しているようです。
風車が動いているのに乳母車は止まっているという対比が、「時間は流れても、心や出来事は取り残される」ような静かな哀しみを表しています。
3.詩とつながる「停まった乳母車」
中原中也の詩『ゆきてかへらぬ』には、「風車を付けた乳母車、いつも街上に停ってゐた」という一節!
詩の中の乳母車も、映画でも「何かが停まっている」ということが重要です。
認識されず素通りされるけど「停まって存在している」、「もういないけれど、動いている存在」。
この「停まっているけれど、存在している」「進んでいるけど、いない」ということに、深い意味があると感じました。
どちらも「過去」「記憶」「戻れない時間」が行きかう複雑な心情が表されています!
その対比的な姿が、観る者の心の深い部分に静かに語りかけているのではないでしょうか。
まとめ
今回は、【ゆきてかへらぬ】2度出てくる乳母車が何を表現しているのか?について、深掘りしました。
それではまとめです。
- 乳母車は「命の始まり」の象徴だが、この映画では「不在」や「終わり」を表している
- 風車は「見えない力」や「流れていく時間」を意味し、乳母車との対比で印象が強まる
- 詩と映画はともに、「戻れない過去」「止まった記憶」「静かな不在」を描いている
『ゆきてかへらぬ』の乳母車は、何も話さないけれど、とても多くのことを語りかけてきます。
この映画を観たとき、その乳母車にどんな気持ちを抱きましたか。
正解・不正解などはなく、直感的に感じたそれが、大切なメッセージなのかもしれません。
映画【ゆきてかへらぬ】で2度出てくる乳母車が気になった方のお役に立てたら幸いです。